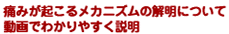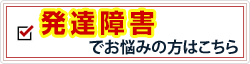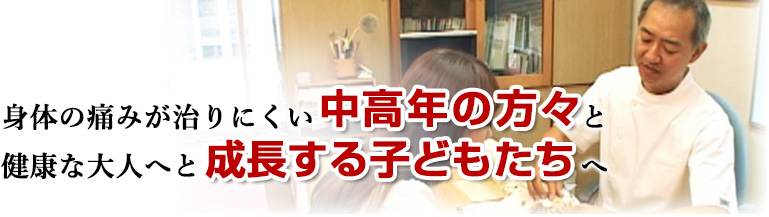
“日本カイロプラクティック師協会指定院”アキヒロカイロプラクティックオフィス
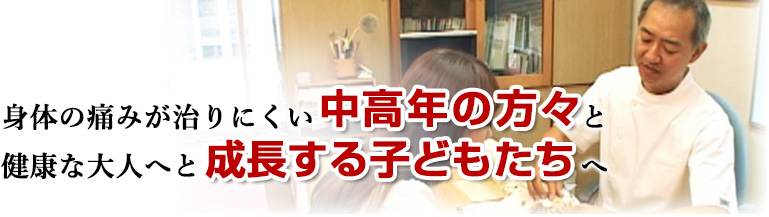
子供のチック症状
- 2016年03月02日
- アキヒロカイロプラクティックオフィス
- スタッフブログ
昨日、施術中に子供のチックについての相談を受けました。
小学校2年生の長女が、最近ひんぱんに瞬きをするチックが出ているとのことです。
「2年前に弟が生まれて私が弟に目を向けているせいか、長女の目が私を求めていることがよくあります。」
「弟の面倒は、よく見てくれているのですごく助かっているのですが?」
「彼女の心にシワ寄せを作っているのでしょうか?」
子供のチックは、3、4歳から始まり7、8歳でピークを迎えるとされています。
チックに関して医学会では、精神分析の視点からの解釈がされていたものが、
最近では神経の病気(脳機能障害としてドーパミン受容体の関連)が注目されています。
ドーパミン?と思われるでしょう。
では、どんな症状があるんでしょう。
症状は、まばたき(瞬目(しゅんもく))、首振り、顔しかめ、口すぼめ、肩上げなど上位の身体部位によく現れますが、
飛び跳ね、足踏み、足けりなど全身に及ぶ運動性チックといわれるものもあります。
また、咳払い、鼻ならし、叫びや単語を連発する発声チックといわれるものもあります。
どれも自分の意思とは関係なく筋肉が動いてしまうものです。
発声チックも筋肉の動いによって起こっています。
一言で言えば、筋肉の働きの乱れです。
パーキンソンの方も手が震える現象があります。
これも意思とは関係ない不随運動です。
パーキンソンの方は、黒質の変性によるドーパミンの分泌が減少したことによるものです。
ここでもドーパミンです。
実は、人間の筋肉の運動は大脳皮質の運動野から筋肉への随意な指令と
大脳皮質から大脳基底核という調節系を経由して筋肉へ不随意な指令を伝える2つの指令は合わさっています。
随意な指令だけでは、動きがロボットのようなカクカクとした動きに待ってしまいます。
調節系からの指令が加わることで滑から動きになります。
調節系の大脳基底核の働きは、様々なところとや物質と関係しています。
そのひとつが中脳の黒質から分泌されるドーパミンです。
医学会の見解は、
子供の場合、発達の未熟さからドーパミンを受け取る働きがが十分にできていないということ。
しかし、チックが発症するまではきちんと受け取れていたということになりますから
発達の未熟さからだけとは断定することは難しいです。
大脳基底核は、感情や記憶の働きをしている辺縁系との関わりが強いため
精神的なストレスが影響することも考えられます。
精神科のドクターも身体的要因と心因的要因の双方の関わりがあると言っています。
ストレスは、辺縁系から自律神経の中枢の視床下部を刺激します。
その結果、交感神経を興奮させます。
交感神経は脳の血管を収縮させますから
長期に血管の収縮が続くと血流が悪くなり
脳細胞の働きが低下を起こします。
大脳基底核の働きも低下すれば、不随運動が起きることがかん変えられます。
現在、小4の男の子の咳のチックの施術を始めたところです。
交感神経を緩和する刺激を与えると咳が止まります。
これは、先に述べたことを裏付ける現象です。
まだ、一時的ですがホームケアと合わせて続けることで症状の改善が期待できます。
家族と力を合わせれば、良い結果が生まれます。
-
- アキヒロカイロプラスティックオフィス
- 診療時間
- 午前:9:00~11:30
午後:14:00~19:00
*土・日の午後の受付は14:00-17:00 - 休診日
- 月曜日・水曜日
※ただし急患の場合はご連絡下さい - 交通アクセス
- 小田急相模原駅 徒歩6分
- 郵便番号
- 〒252-0313
- 住所
- 相模原市南区松が枝町10-6
(※駐車場有り) - 電話番号
- 042-748-2053
- >>詳しくはこちら
-
- 患者様がよくお越しになられる地域
-
- 相生
- 相原
- 青葉
- 旭町
- 麻溝台
- 新磯野
- 磯部
- 鵜野森
- 大島
- 大野台
- 大山町
- 小山
- 鹿沼台
- 上九沢
- 上鶴間
- 上鶴間本町
- 上溝
- 上矢部
- 北里
- 共和
- 向陽町
- 古淵
- 小町通
- 栄町
- 相模大野
- 相模湖町小原
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町千木良
- 相模湖町与瀬
- 相模湖町与瀬本町
- 相模湖町若柳
- 相模台
- 相模台団地
- 相模原
- 桜台
- 下九沢
- 下溝
- 新戸
- 水郷田名
- すすきの町
- 清新
- 相南
- 相武台
- 相武台団地
- 当麻
- 高根
- 田名
- 田名塩田
- 中央
- 千代田
- 津久井町青根
- 津久井町青野原
- 津久井町青山
- 津久井町太井
- 津久井町鳥屋
- 津久井町長竹
- 津久井町中野
- 津久井町根小屋
- 津久井町又野
- 津久井町三井
- 津久井町三ケ木
- 並木
- 西大沼
- 西橋本
- 二本松
- 橋本
- 橋本台
- 光が丘
- 氷川町
- 東大沼
- 東橋本
- 東淵野辺
- 東林間
- 富士見
- 双葉
- 淵野辺
- 淵野辺本町
- 文京
- 星が丘
- 松が枝町
- 松が丘
- 御園
- 緑が丘
- 南台
- 南橋本
- 宮下
- 宮下本町
- 元橋本町
- 弥栄
- 矢部
- 矢部新町
- 豊町
- 陽光台
- 横山
- 横山台
- 由野台
- 若松