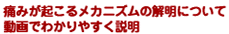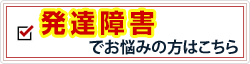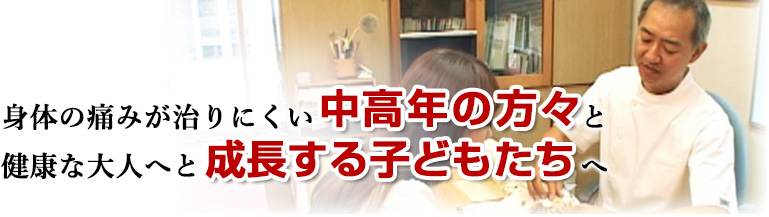
“日本カイロプラクティック師協会指定院”アキヒロカイロプラクティックオフィス
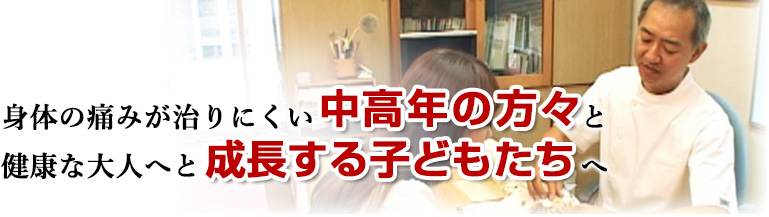
何故、赤ちゃんは物を口に入れるの?
- 2024年09月27日
- アキヒロカイロプラクティックオフィス
- スタッフブログ
赤ちゃんは、なんでも口に入れる時期がある
生後5か月くらいになると赤ちゃんは好奇心のおもむくまま、自分の気になる物などに手を伸ばして、触ったり、つかんだり、口に入れたがったりするようになります。
親は、「飲み込んだら危険」と思い奪い取ってしまったり、「汚い」と思いあらかじめ舐めそうなものを消毒したりしていると思います。
確かに、飲み込んでしまうと危険な場合がありますので、直径38ミリ以下の物は気を付けたほうが良いとのことです。
でも何故、赤ちゃんは物を口に入れるのでしょうか?
赤ちゃんは,まだ感覚がすべて発達していません。
神経発達から見ると「味」、「触り心地」、「噛んだ感じ」を調べるためと言われています。
さらに大事なこととして、「腸内細菌を増やす」ためです。
生まれたばかりのパンダの赤ちゃんは、土をなめたりお母さんのうんちをなめたりしています。
これは、笹を消化してくれる腸内細菌を増やすためです。
人間の子どもも、なめたり口に入れることで生活環境に存在している土壌菌をはじめとした様々な菌を取り入れることで、生きるために必要な腸内細菌を増やしています。
しかし、汚いからといって全ての物をアルコール消毒しがちです。
公園でも「砂場は、猫の糞があるかもしれないので汚いから遊ばせない」人もいるようです。
確かに命に係わる破傷風菌がいますが、予防接種で防ぐことが出来ます。
土壌には、子どもの免疫力や腸の働きに必要な菌が沢山います。
生まれたての赤ちゃんは無菌状態ですが、初乳を飲むことから始まり、様々な人や物、食べ物、土などの自然に触れることで菌を獲得していきますが、獲得する菌の種類は人によって違います。
赤ちゃんの腸内フローラは、生後1歳半でほぼ9割が決まってしまい、これが生涯の腸の土台となります。
3歳までは、腸内細菌の獲得活動は続きますが、それ以降は菌の種類は増えることはありません。
物を口に入れる行為は、味覚や触覚の発達によってなくなります。
赤ちゃんの腸内細菌の種類を増やすための行為を見守ってください。
参考図書:藤田紘一郎著「脳はバカ、腸はかしこい」
-
- アキヒロカイロプラスティックオフィス
- 診療時間
- 午前:9:00~11:30
午後:14:00~19:00
*土・日の午後の受付は14:00-17:00 - 休診日
- 月曜日・水曜日
※ただし急患の場合はご連絡下さい - 交通アクセス
- 小田急相模原駅 徒歩6分
- 郵便番号
- 〒252-0313
- 住所
- 相模原市南区松が枝町10-6
(※駐車場有り) - 電話番号
- 042-748-2053
- >>詳しくはこちら
-
- 患者様がよくお越しになられる地域
-
- 相生
- 相原
- 青葉
- 旭町
- 麻溝台
- 新磯野
- 磯部
- 鵜野森
- 大島
- 大野台
- 大山町
- 小山
- 鹿沼台
- 上九沢
- 上鶴間
- 上鶴間本町
- 上溝
- 上矢部
- 北里
- 共和
- 向陽町
- 古淵
- 小町通
- 栄町
- 相模大野
- 相模湖町小原
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町千木良
- 相模湖町与瀬
- 相模湖町与瀬本町
- 相模湖町若柳
- 相模台
- 相模台団地
- 相模原
- 桜台
- 下九沢
- 下溝
- 新戸
- 水郷田名
- すすきの町
- 清新
- 相南
- 相武台
- 相武台団地
- 当麻
- 高根
- 田名
- 田名塩田
- 中央
- 千代田
- 津久井町青根
- 津久井町青野原
- 津久井町青山
- 津久井町太井
- 津久井町鳥屋
- 津久井町長竹
- 津久井町中野
- 津久井町根小屋
- 津久井町又野
- 津久井町三井
- 津久井町三ケ木
- 並木
- 西大沼
- 西橋本
- 二本松
- 橋本
- 橋本台
- 光が丘
- 氷川町
- 東大沼
- 東橋本
- 東淵野辺
- 東林間
- 富士見
- 双葉
- 淵野辺
- 淵野辺本町
- 文京
- 星が丘
- 松が枝町
- 松が丘
- 御園
- 緑が丘
- 南台
- 南橋本
- 宮下
- 宮下本町
- 元橋本町
- 弥栄
- 矢部
- 矢部新町
- 豊町
- 陽光台
- 横山
- 横山台
- 由野台
- 若松