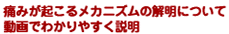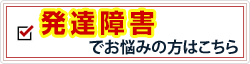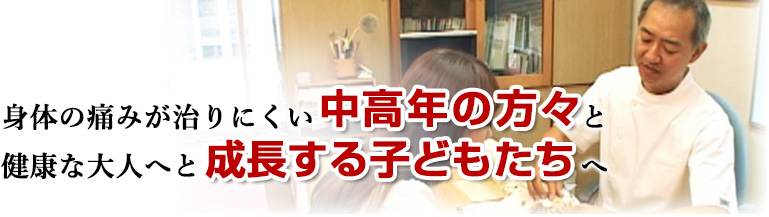
“日本カイロプラクティック師協会指定院”アキヒロカイロプラクティックオフィス
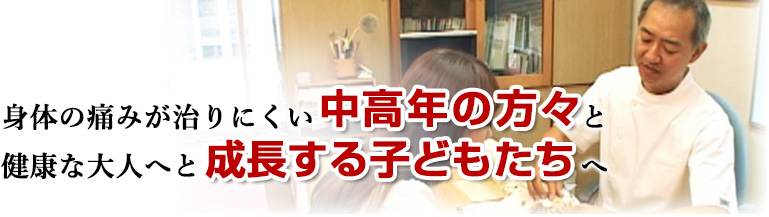
著書「発達障害にクスリはいらない!」から学ぶ発達障害
- 2025年03月29日
- アキヒロカイロプラクティックオフィス
- 子どものカラダ
私たちは、日頃身体に不調が生じると医療にかかり薬を処方してもらうことが当たり前になっていて、鼻水、咳が出て発熱すると内科で風邪薬をもらって飲むと安心します。
本来は、身体の攻撃力(免疫)が備わっているので、薬を飲む前に栄養のあるものを食べて身体を温め十分な睡眠をとらせることが必要なのです。
数日たっても症状が改善しない場合は、免疫力を上回るような病原体が侵入した可能性もあるので、病院で検査をしてもらい原因を特定して必要な薬を処方してもらうことが必要でしょう。
子どもの発達における障害も同じです。すぐに薬に頼るのではなく、薬を飲む前にできることが沢山あります。
カイロプラクティックでは、脳の働きを調べる指標として、『栄養』、『酸素』、『刺激』の3つを大切にしています。
この3つが、満たされていない状態で、薬を与えたとしても期待通りに効くわけがありません。脳への栄養と酸素が十分供給されることが基本になって、神経の刺激が脳の発達を促すことに結びつきます。
発達障害を引き起こしている子に多いのが、偏食による腸の働きの悪さから生じる下痢、便秘です。腸内環境が悪いと栄養の吸収が悪くなり、腸の炎症が全身の炎症を引き起こし酸素の供給も悪くなります。子どもの脳は成長段階であり、様々な刺激を受け取りそれに応えるように神経伝達を増やして、様々なことがスムーズに行えるように調整し発達していきます。
薬物による介入は自己調整力を発達させることとは違います。
神経伝達を薬に頼ってしまい、自分で神経伝達の調整力を促せなくなってしまうことも考えられます。
薬物によって一時的に症状が緩和したからと言って、長期間服用することでじっと座っていられず、絶えず体を動かしたり、うろうろ歩き回ってしまうような行動をとるアカシジアという副作用が出ることがあります。
一般の方は、副作用が出ていても発達障害の症状と見分けがつきにくいものです。
また、薬を止めるときに様々な離断症状が出ることがあります。最初の受診や簡単な問診だけで服薬を始めるのは避けたいものです。
薬を出されそうになったら、医師に「まずは食事や生活を改善して様子を見たいのですが・・・・」などと相談してみましょう。
もし薬を使うことになった場合は、あくまでも薬は一時的なサポートととらえて、薬に頼り切るのではなく、食事や生活習慣の改善を進めていきましょう。
腸の環境が良くなった状態で脳を刺激するメソッドを行うことで脳の発達を促すことにつながります。
最近では、発達障害の改善に役立つとされる種々のメソッドが紹介されています。
カイロプラクティックのブレインバランスメソッドがその一つと言えます。
薬を使うのは最終手段にして、その前にできることをやってみましょう。
参考図書:内山葉子・国光美佳著「発達障害にクスリはいらない」
-
- アキヒロカイロプラスティックオフィス
- 診療時間
- 午前:9:00~11:30
午後:14:00~19:00
*土・日の午後の受付は14:00-17:00 - 休診日
- 月曜日・水曜日
※ただし急患の場合はご連絡下さい - 交通アクセス
- 小田急相模原駅 徒歩6分
- 郵便番号
- 〒252-0313
- 住所
- 相模原市南区松が枝町10-6
(※駐車場有り) - 電話番号
- 042-748-2053
- >>詳しくはこちら
-
- 患者様がよくお越しになられる地域
-
- 相生
- 相原
- 青葉
- 旭町
- 麻溝台
- 新磯野
- 磯部
- 鵜野森
- 大島
- 大野台
- 大山町
- 小山
- 鹿沼台
- 上九沢
- 上鶴間
- 上鶴間本町
- 上溝
- 上矢部
- 北里
- 共和
- 向陽町
- 古淵
- 小町通
- 栄町
- 相模大野
- 相模湖町小原
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町寸沢嵐
- 相模湖町千木良
- 相模湖町与瀬
- 相模湖町与瀬本町
- 相模湖町若柳
- 相模台
- 相模台団地
- 相模原
- 桜台
- 下九沢
- 下溝
- 新戸
- 水郷田名
- すすきの町
- 清新
- 相南
- 相武台
- 相武台団地
- 当麻
- 高根
- 田名
- 田名塩田
- 中央
- 千代田
- 津久井町青根
- 津久井町青野原
- 津久井町青山
- 津久井町太井
- 津久井町鳥屋
- 津久井町長竹
- 津久井町中野
- 津久井町根小屋
- 津久井町又野
- 津久井町三井
- 津久井町三ケ木
- 並木
- 西大沼
- 西橋本
- 二本松
- 橋本
- 橋本台
- 光が丘
- 氷川町
- 東大沼
- 東橋本
- 東淵野辺
- 東林間
- 富士見
- 双葉
- 淵野辺
- 淵野辺本町
- 文京
- 星が丘
- 松が枝町
- 松が丘
- 御園
- 緑が丘
- 南台
- 南橋本
- 宮下
- 宮下本町
- 元橋本町
- 弥栄
- 矢部
- 矢部新町
- 豊町
- 陽光台
- 横山
- 横山台
- 由野台
- 若松